「スマホ認知症」とは? 原因・症状と今すぐできる対策&寝る前スマホ習慣の見直し方法をご紹介します
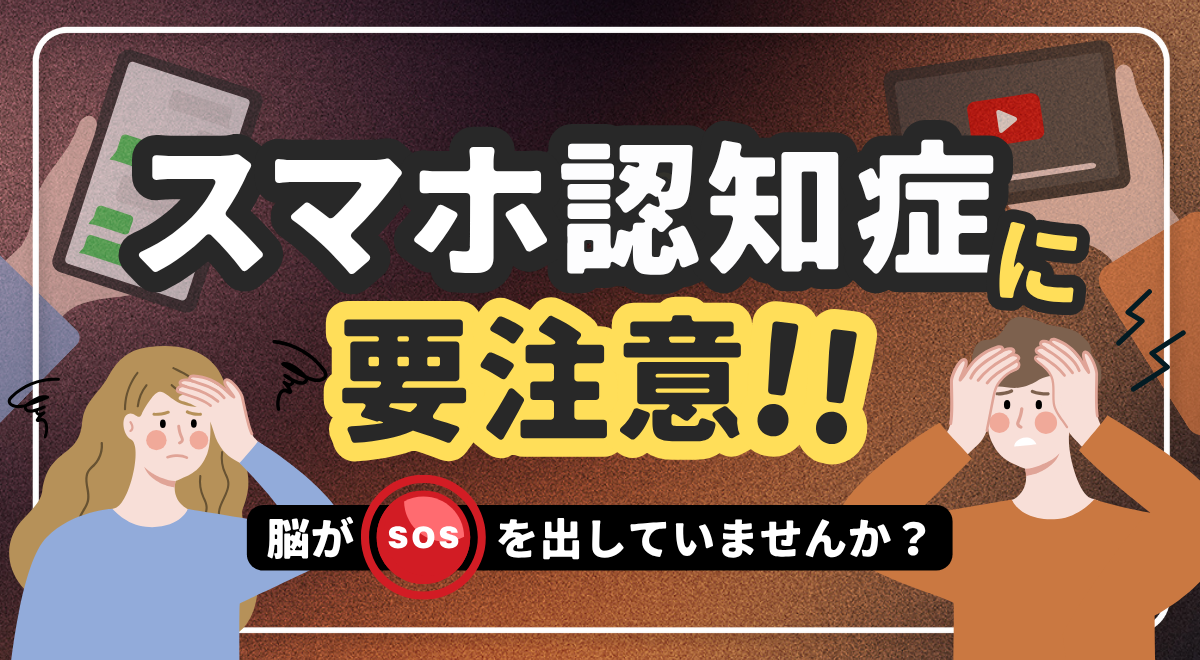
「スマホ認知症」という言葉をご存知でしょうか? ・人の名前や言葉がすぐに出てこない ・やろうと思っていたことをすぐ忘れてしまう ・なんとなくやる気が出ない ・寝ても疲れがとれず、朝からぼんやりしている こうした症状がある方は「スマホ認知症」と呼ばれる現代型の脳疲労を起こしている可能性があります。
このブログでは、スマホ認知症の実態とその対策についてお話ししていきます。今日からほんの少しスマホとの付き合い方を見直してみませんか?
目次
- ・「スマホ認知症」とは?
- ・スマホ認知症は若年層で急増している
- ・こんなサインが出たらスマホ認知症かも?
- ・スマホ認知症の原因は?
- ・スマホ認知症と睡眠障害
- ・スマホ認知症の対策法
- ・「寝る前スマホ」をやめてスマホ認知症を予防しましょう
- ・スマホ認知症を防ぐ!アデッソおすすめの目覚まし時計
- ・スマホはあくまでも便利な「道具」です!
「スマホ認知症」とは?
 スマホ認知症とは、スマートフォンの使いすぎによって記憶力や集中力の低下が引き起こされる状態のことを指します。近年、若年層を中心に認知症ともいえる症状を訴える人が増えていることから、メディアや専門家の間で注目されるようになりました。
スマホ認知症とは、スマートフォンの使いすぎによって記憶力や集中力の低下が引き起こされる状態のことを指します。近年、若年層を中心に認知症ともいえる症状を訴える人が増えていることから、メディアや専門家の間で注目されるようになりました。
「スマホ認知症」と「認知症の違い」
一般的な認知症は、加齢や病気などにより脳の神経細胞がダメージを受け、記憶力や判断力といった認知機能が徐々に低下していく病気です。アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などが代表的で、基本的に高齢者が多く発症します。
一方、スマホ認知症は、長時間のスマートフォン使用によって一時的に脳の働きが鈍くなり、物忘れや集中力の低下といった認知症に似た症状が現れる状態を指します。医学的な正式名称ではなく、脳に器質的な異常があるわけではありません。
しかし、スマホ依存が進むと脳の柔軟に働く力に悪影響が出て、症状の回復に時間がかかるケースもあるとされています。そのため、「自分もスマホ認知症かも?」「スマホ依存な気がする」と感じている方は、単なる疲れと放置せず、早めに対策をしましょう!
脳のメカニズムから見るスマホ認知症
スマホ認知症の背景には、脳の構造や働きが深く関係しています。長時間のスマホ使用で特に影響を受けやすいのが、前頭前野と海馬です。
前頭前野(ぜんとうぜんや)とは? 思考・判断・集中力を司る脳の司令塔です。スマホによるマルチタスクや過剰な刺激でこの部位の機能が低下すると、注意力が続かなかったり、イライラしやすくなったりします。
※マルチタスク 同時に複数の作業をこなす、または短時間で切り替えながら複数の作業を行うことです。スマホとテレビを同時に見る、などがマルチタスクと言われるものです。
海馬(かいば)とは? 記憶を管理する部分です。スマホから得る断片的な情報ばかり繰り返し処理していると、長期記憶として定着しにくくなります。 このように、脳の重要な部位がスマホ使用により日常的に酷使されることで「認知機能の一時的な低下(スマホ認知症)」という現象が起きるのです。
スマホ認知症は若年層で急増している

スマホ認知症が若い世代に増えている理由
スマホ認知症は、高齢者よりもむしろ20代~30代の若い世代で増加傾向にあります。その理由は、以下だと考えられています。
- ・幼少期からスマホに囲まれて過ごしてきた世代であること
- ・生活の中でスマホ利用時間が6時間以上など極端に長い
- ・LINEをしながら食事をするなどマルチタスク状態が常態化している
現代の若者は、幼い頃からスマートフォンが身近にある環境で育ってきたため、常に膨大な情報にさらされ続けています。その影響で脳が疲れやすくなり、記憶力や集中力の低下を招いていると指摘されています。
スマホ認知症はこどもにも?
スマホの過剰使用によるスマホ認知症の症状は、大人に限らず、子どもにも表れてきています。特に注目されているのが、子どもの脳の発達と学習能力への悪影響です。 以前お話しを伺った東北大学加齢医学研究所の川島教授と榊助教は、長年にわたり宮城県仙台市教育委員会と共同研究を続けており、スマホの使用時間が長い子どもほど全国学力テストの成績が低下する傾向があることを明らかにしました。
スマホの使用を1日1時間未満に抑えている子どもたちの方が、1時間以上スマホを使う子どもたちよりも成績が成績がやや高い傾向があり、それ以上スマホを使用している子どもたちは、成績が明らかに低下するという結果が10年以上にわたって繰り返し確認されています。
このような傾向の背景には、「ながら勉強」による集中力の低下や、前頭前野の発達停滞があると考えられています。前頭前野は、思考力・記憶力・自己制御・コミュニケーションなどを担う部分であり、スマホやネット動画の長時間利用によって、この領域の発達が停滞するということが研究で明らかになっています。
スマホを見ながら勉強するというマルチタスクによる集中力の低下や、前頭前野の機能低下は、大人のスマホ認知症と同じメカニズムです。つまり、スマホの長時間使用によって脳の働きが鈍り、記憶力や集中力、判断力などが落ちていくという現象は、子どもにも当てはまるのです。
スマホ認知症は、年齢に関係なく、脳が使われないこと、脳が刺激され続けることで退化していく状態を指します。発達段階にある子どもにとっては非常に深刻なリスクです。
スマホ認知症は現代人が誰でも発症しうる病気です
皆さんは普段どんな時にスマホを利用していますか?
- ・朝アラームを止めてそのままベッドでショート動画の視聴
- ・通勤通学時間に手持ち無沙汰でゲーム
- ・休み時間にSNS
- ・ちょっとした待ち時間にネットニュース
- ・寝る前は友人とのやりとり
など 気がつけば、スマホを手放している時間のほうが少ない、そんな毎日を送っていませんか? 便利で手軽なスマートフォンは、私たちの生活に欠かせない存在となりました。SNSや動画視聴、買い物、ゲームなど、多くの情報やサービスをスマホ一台で利用できます。
しかし、その「便利すぎる道具」が、使い方によっては脳に悪影響を及ぼし、スマホ認知症と呼ばれる状態を引き起こすこともあります。 スマホ認知症は、脳のパフォーマンスを確実に奪っていく日常的なリスクです。さっそく次章でご自身にスマホ認知症の症状が出ていないかチェックしていきましょう。
こんなサインが出たらスマホ認知症かも?
 日々のスマホ使用によって脳はじわじわと疲弊しています。無意識のうちに、スマホ認知症の入り口に立っているかもしれません。 以下のようなサインが現れていたら、脳が疲れているかもしれません。一つでも当てはまるものがあれば、スマホとの付き合い方を見直してスマホ認知症を予防しましょう。
日々のスマホ使用によって脳はじわじわと疲弊しています。無意識のうちに、スマホ認知症の入り口に立っているかもしれません。 以下のようなサインが現れていたら、脳が疲れているかもしれません。一つでも当てはまるものがあれば、スマホとの付き合い方を見直してスマホ認知症を予防しましょう。
・名前や単語が思い出せない 以前はすぐに思い出せていた名前や単語が出てこなくなるのは、記憶の検索機能が鈍っているサインです。記憶を引き出すトレーニングをしていないと、脳の中で情報が散らばってしまい、必要なときに取り出せなくなってしまいます。
・作業に集中できない ミスが増えた やらなきゃいけない事がたくさんあるのに、気づくとスマホを触っていませんか?スマホで絶え間なく通知や情報に触れていると、脳は情報の渋滞を起こし、思考の集中力が続かなくなります。その結果、仕事や家事でケアレスミスが増えたり、勉強に集中できなくなったりする傾向があります。
・スマホの通知が鳴ると必ず反応してしまう 勉強や仕事、家事をしていたり、友達と話していても通知が気になり、通知が鳴ったらすぐにスマホを開いてしまうのはスマホ依存症の1つの症状です。スマホ依存症になっている場合、スマホ認知症の症状が出ている可能性も非常に高いです。 また通知が鳴っていないのに、音がしたような気がしたり、スマホが振動しているような気がしてスマホをチェックしてしまう人も要注意です。
・眠りが浅く、朝スッキリ起きられない 寝る前のスマホ使用は、ブルーライトの影響で脳を刺激し続けます。メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が抑制されるため、眠りが浅くなり、朝起きても疲労感が抜けません。毎朝「起きるのがつらい」「スッキリしない」と感じている場合、スマホによる睡眠障害が原因かもしれません。
・やる気が出ない 気分が沈みがち 前述した通り脳の前頭前野は、意欲や感情のコントロールなど様々な役割を担う重要なエリアです。この部分がスマホの使いすぎで疲弊すると、「気分が落ち込む」「やる気が出ない」といったメンタル面の不調が現れやすくなります。 またSNSの過度な使用も、自分との比較やネガティブな情報によってメンタルを消耗させる一因です。
・外出先でスマホがないと不安になる スマホを忘れると外出中でも何も手につかなくなってしまう事はありませんか?これはスマホ依存の初期症状です。 それだけでなく脳がスマホの情報に頼りすぎているサインでもあります。地図、予定、連絡先など、あらゆる情報をスマホに委ねすぎることで、脳の記憶力や判断力は確実に衰えていきます。
・思考が浅くなったと感じる 前よりも自分の考えがまとまらなかったり、本を読んでも誰かと話していても内容が入ってこない。こういった事が続く場合、脳がスマホの短い文面や短い動画などに慣れてしまっている場合があります。 SNSやニュースアプリなど、断片的な情報ばかりを見ていると、物事を深く考えたり、じっくり読んだりする力が落ちてしまいます。
いくつ当てはまりましたか?これらのサインは、一見日常でよくあることにも思えますが、放っておくと脳のパフォーマンス低下につながっていきます。当てはまる項目があった方は、スマホとの距離感を見直し、スマホ認知症から脳を守りましょう!
スマホ認知症の原因は?
 スマホ認知症のような脳の不具合がなぜ起こるのかについて詳しくみていきましょう。
スマホ認知症のような脳の不具合がなぜ起こるのかについて詳しくみていきましょう。
情報の過剰摂取と脳の酷使
私たちの脳は、本来、インプット(情報の取り込み)とアウトプット(情報の整理・表現)のバランスをとりながら機能しています。しかし、スマートフォンを長時間使用していると、ニュース、SNS、動画など膨大な情報が次々と流れ込み、インプットばかりが過剰になります。
このような情報過多の状態では、脳は休む間もなく働き続け、情報を整理・記憶する前頭葉や海馬に大きな負担がかかります。特に海馬は記憶の中継地点として重要な役割を担っているため、疲弊すると物忘れが多くなる、記憶が定着しない、といった症状が出やすくなります。
また、前頭葉は感情のコントロールにも関係しているため、過度の負荷によって些細なことでイライラする、気分の浮き沈みが激しくなる、など情緒の不安定さも見られるようになります。こうした脳の酷使こそが、スマホ認知症の大きな引き金となっているのです。
便利すぎるスマホの機能
スマホは、検索すれば一瞬で答えが出る、スケジュールも通知してくれる、地図も自動で案内してくれる、とても便利な道具です。しかし、その便利さに頼ってばかりいると、脳が考えたり思い出したりといった働きをしなくなってしまうリスクがあります。
脳は、悩む⇒思い出す⇒考えを整理するといったプロセスを繰り返すことで発達していきます。これは、使えば使うほど鍛えられるものです。ところが、何かあればすぐにスマホに頼る生活を続けていると、脳は働くのを辞め、次第に機能が低下していきます。 自分で考えなくても、思い出さなくてもなんとかなる、そういった状態が長く続くほど、スマホ認知症のリスクは高まっていくのです。
SNSによるストレス・不安の蓄積
何気ない空き時間に、ついSNSを眺めてしまうという方も多いのではないでしょうか。しかし、「いいね」やフォロワー数、他人の華やかな投稿との比較は、脳に慢性的なストレスや不安をもたらします。こうした精神的負荷が積み重なることで脳内ホルモンのバランスが崩れ、記憶力や判断力を担う前頭葉の機能が低下し、やがてスマホ認知症のリスクを高めてしまうのです。
また、ストレスによって睡眠の質が悪化し、さらに脳の回復が阻害されるという悪循環にも陥りやすくなります。
スマホの長期間使用による姿勢への影響
スマホを長時間使用していると、どうしても体を動かす時間が減ります。さらに、前かがみの姿勢を続けることで、首や肩の血流が悪化し、脳への酸素供給にも影響が出る可能性があります。首の自然なカーブが失われる「ストレートネック」になる人も増えており、慢性的な肩こりや頭痛、集中力の低下につながるケースも少なくありません。
このような身体面での変化も、記憶力や集中力の低下といったスマホ認知症の一因になりうるのです。
他者とのコミュニケーション不足
家族や友達と一緒にいてもスマホを触っていてあまり会話をしていない、こういった状況もスマホ認知症の原因の一つになります。 脳は会話やコミュニケーションを通じて活性化されます。他者との会話の機会が減ってしまうと、記憶力や判断力などの認知機能が低下しやすくなるとされています。
睡眠の質の低下
寝る前についついSNSや動画を見てしまう「寝る前スマホ」が習慣になっている人も多いと思いますが、寝る前スマホはブルーライトの影響を受け、寝つきが悪くなり、しっかり眠れない、といった睡眠への悪影響を及ぼします。 寝る前スマホによる睡眠の質の低下は若年層に特に多い事が報告されています。浅い眠りが続くと、脳の記憶力や回復力も下がり、スマホ認知症をさらに悪化させる原因になります。
スマホ認知症と睡眠障害
 寝る直前までスマホを見ていて、いざ寝ようと思ってもなかなか眠れなかった、そんな経験はありませんか?寝る前スマホは、ただ脳を疲れさせるだけでなく、深刻な睡眠障害を引き起こし、脳のパフォーマンスを低下させる悪循環に繋がります。
寝る直前までスマホを見ていて、いざ寝ようと思ってもなかなか眠れなかった、そんな経験はありませんか?寝る前スマホは、ただ脳を疲れさせるだけでなく、深刻な睡眠障害を引き起こし、脳のパフォーマンスを低下させる悪循環に繋がります。
ブルーライトが脳の「眠る準備」を妨げる
スマホの画面から発せられるブルーライトは、脳内のメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を抑制する作用があります。その結果、脳は「今は夜ではない」と勘違いし、睡眠モードに入るのが遅れてしまいます。 この状態が続くと、浅い眠りが慢性化し、脳が十分に休めなくなってスマホ認知症の初期症状(記憶力・集中力の低下、感情の不安定など)として現れやすくなるのです。
寝る直前の情報インプットが脳を興奮させる
SNSや動画は、感情や思考を刺激し、脳を「興奮状態」に保ち続けます。ベッドでスマホを使う習慣があると、脳がリラックスできず、なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚めるといった睡眠の質の低下を招くのです。 このような状態が続くことで、日中のパフォーマンスが低下し、さらにスマホ依存に拍車がかかる、という悪循環が起きやすくなります。まさに、スマホ認知症が進行する典型的なパターンです。
睡眠不足は記憶の整理を妨げる
本来、睡眠中にはその日に得た情報を脳が整理・定着させる大切な時間があります。しかし、質の悪い睡眠が続くと、この記憶の整理機能がうまく働かなくなり、スマホ認知症の進行を加速させてしまいます。 最近、物忘れが多かったり、何だか上手に話せない、と感じている方は、スマホによる睡眠への影響を疑ってみることが重要です。
スマホの使いすぎによる睡眠障害とスマホ認知症
「最近なんだか頭がボーッとする」「疲れが抜けにくい」と感じている方は、スマホの使いすぎによる睡眠障害、そしてそこから派生するスマホ認知症の症状が出ている可能性があります。 「そのうちしっかり眠れば回復する」と思っていても、スマホ依存が進んでいる場合は、そもそも質の良い睡眠をとること自体が難しくなっていることもあります。
スマホ認知症の対策法
 スマホは現代の必需品ですが前述した通り、脳の働きを妨げる物にもなってしまいます。スマホ認知症の予防・改善するために出来ることをご紹介しますので、今日から出来ることを少しずつ実践していきましょう。
スマホは現代の必需品ですが前述した通り、脳の働きを妨げる物にもなってしまいます。スマホ認知症の予防・改善するために出来ることをご紹介しますので、今日から出来ることを少しずつ実践していきましょう。
1.自分がどの程度スマホを使っているかを把握しましょう
まずは、自分がどれだけスマホに時間を使っているかを把握しましょう。iPhoneの「スクリーンタイム」や、Androidの「デジタルウェルビーイング」などを使えば、アプリごとの使用時間がすぐに確認できます。 1日5〜6時間以上スマホを使っている人は、脳への負荷がかなり高い状態です。特に連続使用が続くと、脳が休む隙を失います。
2. 情報のインプットとアウトプットのバランスをとりましょう
スマホから得た情報をそのままにせず、誰かに話したり、メモにまとめたりして、アウトプットするくせをつけましょう。 アウトプットには、記憶を定着させ、脳の回路を活性化させる効果があります。ただ読むだけ、見るだけの受け身状態が続くと、脳の働きは鈍っていきます。
3. 脳の休息時間を意識的にとりましょう
脳を疲れさせないためには、意図的な休息が必要です。脳の休息におすすめの方法をご紹介します。 ・10〜20分の昼寝 脳が回復する時間を与えましょう ・スマホを見る目的を明確にする なんとなくスマホを開くのを意識的に避けましょう ・自然の中でぼーっとする時間を持つ デジタルのものから離れる時間をとりましょう ・寝る前3時間はスマホから距離を取る 脳の回復とリセットに一番おすすめの方法は、夜にスマホをいじらない事です。
「寝る前スマホ」をやめてスマホ認知症を予防しましょう
 スマホ認知症の予防・改善のために特に見直してほしいのが、寝る前スマホです。寝る前のスマホ使用は眠りを浅くし、睡眠時間を短くし、脳の回復を妨げます。結果として、記憶力の低下、感情の不安定化、集中力の欠如といったスマホ認知症の症状につながりかねません。
スマホ認知症の予防・改善のために特に見直してほしいのが、寝る前スマホです。寝る前のスマホ使用は眠りを浅くし、睡眠時間を短くし、脳の回復を妨げます。結果として、記憶力の低下、感情の不安定化、集中力の欠如といったスマホ認知症の症状につながりかねません。
枕元にスマホを置いていませんか?
スマホを寝室に持ち込み枕元に置いて置く事を辞めるだけで、 ・寝る直前のSNSチェックや動画視聴の誘惑が減る ・脳の興奮が抑えられ、自然と入眠しやすくなる ・夜中に目覚めても、ついスマホを見てしまうというスマホ依存ループを断ち切れる このようにスマホ認知症の予防にもつながる効果が期待できます。
スマホ認知症改善のためにスマホはリビングに置いておきましょう
実際皆さんは、スマホを見てから寝た時とスマホを見ずに寝た時で目覚めの感覚が違う、という体験をしたことがあるのではないでしょうか? とはいえ、寝る前の自由時間にスマホを見たいという気持ちもとてもよくわかります。
おすすめは、「スマホを寝室に持ち込まない」ことです。寝る前3時間スマホを触らない、というのはハードルが高いかもしれませんが、寝室に持ち込まないことは出来るのではないでしょうか?
アデッソがおすすめするスモールステップはこちらです!
- ・アラームを目覚まし時計に置き換える
- ・スマホはリビングなどの別の部屋に置いて充電しておく
最初は不便に感じるかもしれませんが、寝る直前にスマホを見ることを避けるだけで、数日後には、朝スッキリ起きられる、寝つきがよくなった、日中の集中力が上がった、といった変化に気づくはずです。 アデッソでは、寝室にスマホを持ち込まず、代わりに目覚まし時計で目覚めることにより、皆さんのスマホ認知症の予防と改善だけでなく、睡眠の質の改善、睡眠時間の確保、脳と体のリズムを取り戻すお手伝いをしたいと考えています。
スマホ認知症を防ぐ!アデッソおすすめの目覚まし時計
・アデッソの看板商品!スマホのバイブレーションよりも何倍も強い振動でスッキリ目が覚めます
・アデッソの振動目覚ましの中でも強力振動+大音量!普通の目覚ましでは起きられない方におすすめです
・お部屋に馴染むオールブラックデザイン!4つの異なる時刻にアラームを設定できます
スマホはあくまでも便利な「道具」です!
スマホ認知症は現代人が気を付けなくてはならない脳の問題の1つです。 私たちの脳は、インプットとアウトプットのバランスがとれている状態で一晩しっかりと眠ることにより情報を整理し、記憶を定着させ、感情を落ち着かせる準備をしています。そのためにも、寝る直前くらいはスマホから距離をとって、脳を休ませる時間を作ってあげることが大切です。
デジタルデトックス、というと難しく感じますが、寝室にスマホを持っていかない、というだけであれば実践出来る方も多いのではないでしょうか? 皆さんの脳と心の健康を守るために、少しでもアデッソの時計が役立てば幸いです!スマホ認知症の予防、改善のためにぜひ目覚まし時計で気持ちの良い朝をスタートさせましょう!





