『スマホ育児が子どもを壊す』著者の石井光太が語る、子どもの“非スマホ時間”の重要性
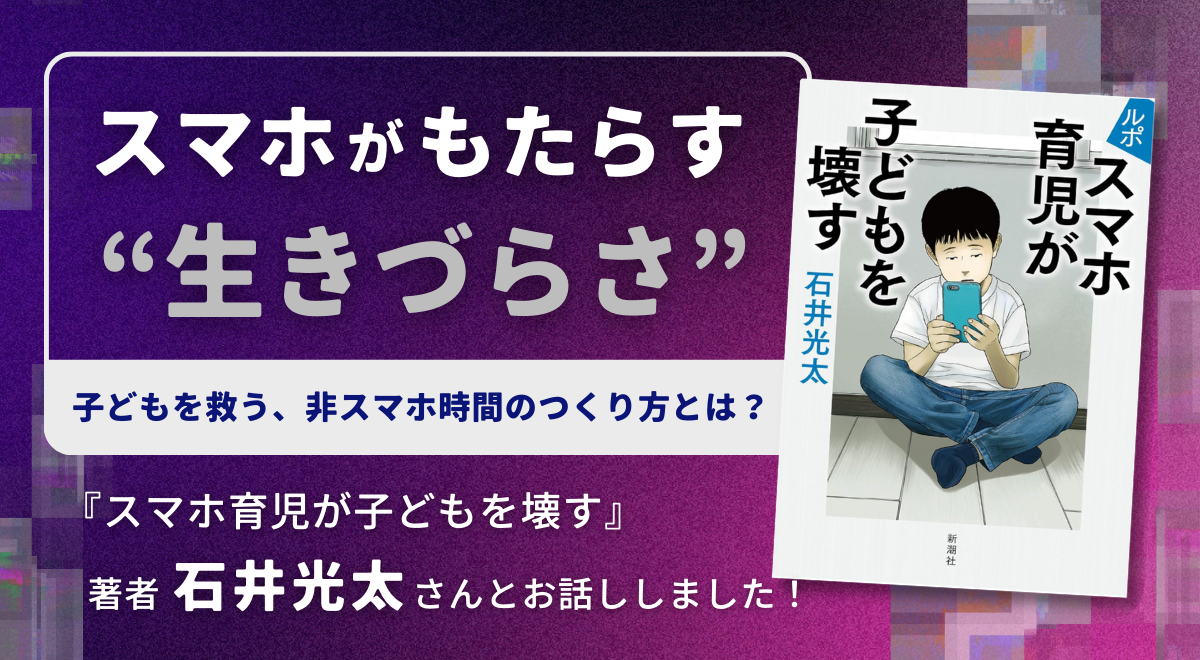
いまやスマホは子どもから大人まで、幅広い世代が当たり前のように使うものとなりました。しかし、「スマホ依存」という言葉が存在するように、スマホは必ずしも便利な側面だけではありません。 実際にオーストラリアでは、「子どもの心身の健康にリスクを与える」との理由から、14歳未満の子どものSNS利用を禁止する法案を年内に提出すると発表がありました。
世界的にも子どもたちのスマホ使用に関する関心が高まっている中、子どものスマホとの付き合い方について考える親もいるのではないでしょうか。 今回は、著書『スマホ育児が子どもを壊す』を出版したルポライターの石井光太さんをゲストに迎え、アデッソ 代表取締役の長谷川大悟、副社長の長谷川賢悟、モデレーターの佐藤と「スマホ育児」について話します。 
記事サマリ
- ・スマホ依存は社会全体の問題であり、子どもの成長に影響を与える現代の象徴となっている
- ・体育座りや投げる動作ができない、視力低下、SNS中心の人間関係など子どもの身体や心に変化が現れている
- ・子どもの成長は断片的に見るのではなく、幼少期から高校生までの流れ全体を意識することが重要
- ・スマホ自体が悪いのではなく基礎力が育っていない子どもに与えると依存やトラブルにつながる
- ・親や教育者がスマホ使用を管理し手本を示すことが子どもの健全な成長に直結する
- ・家族の会話や部活などスマホを使っていない時間を充実させることが依存を防ぎ、将来に必要な力を身につける助けとなる
スマホの問題は現代社会の問題
 佐藤(モデレーター):世の中にはスマホの使い方に対して警鐘を鳴らしている方も少なからずいますが、スマホがあまりにも便利すぎて、現状としてその声が十分に届いていないと感じます。
佐藤(モデレーター):世の中にはスマホの使い方に対して警鐘を鳴らしている方も少なからずいますが、スマホがあまりにも便利すぎて、現状としてその声が十分に届いていないと感じます。
実際に、私たちも独自にお客様2,000人ほどにアンケートを行いました。2018年ごろに『スマホ脳』が話題になりましたが、その本を「知っていて、今でも気にしている」と答えたのは全体の15%にすぎませんでした。さらに、15%は「知っているが記憶にはあまり残っていない」。約70%が「その本を知らない」と回答したんです。
つまり、全体のうちわずか15%ほどしか、スマホの使い過ぎに対して危機感を抱いているわけではないんですよね。それでも、その15%の人たちが少しでも危機感を持ち始めれば、社会が動くきっかけになるのではないかと考えています。
だからこそ今回の対談では、著書『スマホ育児が子どもを壊す』を出された石井さんのように、警鐘を鳴らしている方とお話しすることで、一緒にメッセージを発信していけたらなと思っております。
長谷川 賢悟(以下、賢悟):著書『スマホ育児が子どもを壊す』を見た時、まずタイトルの持つメッセージ性がとてもストレートで衝撃を受けました。何か意図があるのでしょうか。
石井光太(以下、石井):この本が指摘しているのは、単にスマホの問題だけではなく、現代の社会そのものです。特に子どもたちを取り巻く新しい環境がどのような影響を与えているか、という点を指摘しており、未就学児から高校生まで、各成長段階においてその影響を順を追って解説しています。
特に、過去10年で子どもたちの環境を大きく変えた要因の一つとしてスマホが挙げられていて、これはまさに現代社会の変化の象徴といえます。スマホを通じて間接的に影響を受けることで、子どもたちが気づかぬうちに生きづらさを感じることが増え、体験や人間関係の認識が大きく変わってしまっていることが問題として浮き彫りになっているんです。
例えば、「ハイハイをしたことがない子ども」や「体幹が弱く、体育座りすらできない子ども」が増えていること。また、友人や恋人といった人間関係の概念自体が変わってしまい、それに伴って子どもたちが無意識に感じる苦しさや困難も増えているんです。
ただし、スマホが100%悪いとは言い切れません。むしろ、スマホ自体が悪者というわけではないんですよね。しかし、スマホを通じて受ける影響が子どもたちにとって損害を与えているのであれば、それをきちんと直視しなければなりません。
そうした損害が彼らの成長や人生にどのような悪影響を及ぼしているのかを理解することが重要です。 そのため、私はこの本のタイトルを『スマホ育児が子どもを壊す』としました。子どもたちの健全な成長や未来に影響を与えるスマホの使い方について、警鐘を鳴らしたかったからです。
賢悟:小学生くらいの子どもがスマホをのめり込むように見ている表紙のイラストも印象的です。
石井:「スマホ育児」という言葉を聞くと、どうしても赤ちゃんや幼児期だけに限定された話のように思われがちです。しかし、実際にはもっと広い年齢層、特に小学生や中学生にも深く影響を与えています。そのため、今回の表紙は鈴木マサカズさんにお願いして、赤ちゃんではなく、小学生くらいの子どもをイメージしてデザインしてもらいました。
子どもの成長過程を断片的ではなく全体として見る
 佐藤:『スマホ育児が子どもを壊す』を執筆された経緯について教えてください。
佐藤:『スマホ育児が子どもを壊す』を執筆された経緯について教えてください。
石井:学校で講演をしたり、取材を通じて子どもたちと接する中で、現代の子どもたちは急速な変化に直面することが多いと感じました。身体的な変化としては、体育座りやしゃがむことができない、ソフトボール投げができない、視力の急激な低下といった現象が顕著に見られています。また、友達関係や恋愛関係も大きく変化しています。
例えば、LINEなどのSNSを使って簡単に関係を切ったり、出会いからデート、交際まですべてオンラインで完結してしまうことが一般的になりつつあります。さらには、物理的に一緒にいても、心の距離があるように感じるような、友達という概念自体が変わってきています。
こうした変化を見て、「最近の子どもたちは変だ」「けしからん」といった表面的な批判に終始するのではなく、「なぜ子どもたちがこのような状況に至っているのか」と、その背景や原因を解明しなければ、根本的な理解には至りません。
これが、私が取材を始める際に最も感じたことの1つであり、取材や研究を通して、その背後にある要因を明らかにしたいと思ったきっかけです。現代の子どもたちが直面している問題は、単なる世代の違いや技術の進歩に留まらず、より深い社会的・心理的な要因が絡み合っていることを、私たち大人が理解し、それに対処していく必要があると強く感じます。
賢悟:この本では未就学児から高校生までを扱っていますが、感じたことなどがあれば知りたいです。
石井:各教育段階の先生たちがそれぞれの担当する年齢層にしか焦点を当てていない点です。例えば、小学校の先生は小学生を見ていて、その前段階で何が起こったかという視点はあまり持っていません。中学校の先生も同じく、中学生の現状だけを見ていますが、その子どもたちが小学生だった時の状況や、さらに遡って幼少期にどんな影響を受けたのかは把握していないんです。
体育座りができない子どもたちの増加や、友達や恋人といった人間関係の認識が変化していることに関しても、一連の成長過程に影響があるはずなのに、それを深く掘り下げてみようとする視点が欠けているように思います。
また、保育園や幼稚園の先生たちも、子どもたちがその後どう成長していくのかを知らない場合が多いです。例えば、離乳食が適切に与えられなかった子どもや、歩行がうまくできない子どもたちが、やがて小学校や中学校に入ってどんな困難に直面するのかを見通すことができていないんですよね。
このように、各段階の専門家たちが、その前後の影響や背景を理解しないまま子どもたちを見ているため、全体的な視点が欠けてしまっているんです。この本では、そうした視点を持つことの重要性も伝えたかったという思いがあります。
「スマホは悪いものではない」
 佐藤:ここからはスマホがもたらす影響について、伺いたいと思います。率直に、石井さんは子どものスマホ使用についてどう感じていますか。
佐藤:ここからはスマホがもたらす影響について、伺いたいと思います。率直に、石井さんは子どものスマホ使用についてどう感じていますか。
石井:今の社会では、スマホが良いか悪いか、流行っているかどうかといった表面的な議論が行われています。私自身はスマホを必ずしも悪いものとは考えていません。むしろ、特定の目的において大きな助けになっていると感じます。 例えば、野生動物と戦う際、刀を持っている方が強いのと同様に、スマホも適切に使えば大きな武器となります。しかし、戦うための体力や戦略、勇気がない人が刀を持っても、意味がありません。
このことはすべての能力に当てはまります。私の仕事で言えば、取材力や表現力を持つ人がスマホを使うと、大量のデータを集めるツールとして活用できるでしょう。その結果、より優れた記事を書くことができるはずです。しかし、これらの能力がない人がスマホを持っても、結局AIに頼ることになってしまいます。
現在の問題は、基礎的な能力が育っていない子どもたちがスマホを手にしてしまうことです。子どもに突然刀を渡すと、無秩序に振り回してしまうのと同じです。それがスマホに関連するトラブルや依存の原因になっています。社会全体でスマホの存在意義を真剣に考え、基礎となる能力を育てたうえでスマホを持たせる必要があります。
佐藤:適切にスマホを使うことが求められるとおっしゃっていましたが、やはり親世代からスマホがもたらす影響について認識することが大切だと考えていますか。
石井:そうですね。一日にスマホをどれくらい使用するのが適切か、どのように使えば良いのかを観察し管理する大人の役割が求められます。現状では、そこに意識が向いている親とそうでない親との間に大きな隔たりがあるように感じます。 昔は、子育てにおいて社会全体での共通認識が存在し、「これをやらせておけば大丈夫」といった考え方があったため、多くの人が同じように育てていました。
しかし、今はそれぞれの親が子どもに対して個別に指導し、管理しなければならない時代です。そのため、できる家庭とできない家庭の格差が広がってきています。
周囲の大人が手本を示す
 賢悟:結局、大人もスマホに依存しているのではないかと感じています。私自身、子どもがいますが、スマホを渡すとたしかに楽になります。その便利さに流されず、あえてスマホを与えないという選択をするのは簡単なことではありません。 意識のある親にはメッセージを伝えれば受け取ってもらえるでしょうが、スマホ中毒について無関心で楽な道を選んでいる親に対しては、何をどう伝えるかが難しい課題です。
賢悟:結局、大人もスマホに依存しているのではないかと感じています。私自身、子どもがいますが、スマホを渡すとたしかに楽になります。その便利さに流されず、あえてスマホを与えないという選択をするのは簡単なことではありません。 意識のある親にはメッセージを伝えれば受け取ってもらえるでしょうが、スマホ中毒について無関心で楽な道を選んでいる親に対しては、何をどう伝えるかが難しい課題です。
石井:親自身が自覚しなければ、状況を改善するのは難しいと思います。そうなると、他の親たちが良い手本を示すのも一つの手かなと。例えば、親が本を読んでいる家庭では、子どもも自然と本を読む傾向があります。これはほぼ間違いありませんが、逆に親が本を読まなければ、子どもも読むことはないでしょう。
子どもは親を見て、「これが普通だ」と感じることが多いので、それが彼らの行動に影響を与えます。ただし、周囲の大人が良い手本を示すことで親の認識を変えられる可能性もあります。 特に中学生や高校生になると、親よりも周囲の大人の影響を受けることが増えます。
小学生までは親が全てですが、思春期になると親の言葉は無視されがちです。なので、教育者や部活動の顧問など、他の大人たちが良い例を示すことも重要です。自覚のない親に働きかけて意識を変えるのは難しいですが、周囲の大人がその自覚を持ち、それを示すことがより効果的だと思います。
「かっこいい」が生み出す依存
 佐藤:タバコやアルコールは、健康に悪影響を及ぼすことが広く認識されるようになり、喫煙率やストロング缶の消費が減少しています。一方で、スマホ使用についてはそういった流れは見えません。スマホを適切に使おうという認識が広まりにくい中で、少しでも大人の認識を変えるためにできることとは何でしょうか。
佐藤:タバコやアルコールは、健康に悪影響を及ぼすことが広く認識されるようになり、喫煙率やストロング缶の消費が減少しています。一方で、スマホ使用についてはそういった流れは見えません。スマホを適切に使おうという認識が広まりにくい中で、少しでも大人の認識を変えるためにできることとは何でしょうか。
石井:これは個人的な意見ですが、人がタバコをやめるようになったのは「悪い」と言われたからではないと思います。タバコの健康への影響については、もう50年以上前から言われてきましたし、それでも吸い続ける人は多かったですよね。なので、単に「体に悪い」と言われただけでは、人間はやめないのではないかと感じます。
では、なぜタバコをやめる人が増えたかというと、社会全体でタバコを吸うことが「かっこ悪い」とされるようになったからです。たった20年前、いや数年前までは、中学校や高校の先生が生徒にタバコを注意するのが一番の悩みでした。その理由は、生徒たちがタバコを「かっこいい」と思っていたからです。
実際、学生にとってタバコは美味しいものではなく、単にそのファッション性に惹かれていたのです。 お酒についても同じことが言えます。最初は苦いビールを我慢して飲んでいたのは、飲むこと自体が「かっこいい」とされていたからです。しかし、その瞬間に「かっこ悪い」となれば、誰も飲まなくなります。
結局、特に若い世代においては、何が「かっこいい」かという文化や風潮を作ることで、流れが一気に変わるように感じます。 スマホに当てはめると、ブランドが「それを持つことがかっこいい」と演出していることが考えられます。普通に考えれば、あんなに高価なものは買わないはずですが、その「かっこよさ」が魅力となっているのです。
スマホから得られるスキルとリアルな生活で得られるスキル
 賢悟:やはり国やメディア、企業の働きかけが十分ではないと感じます。この問題に対して、実際には誰もがあまり働きかけていないように思えます。もちろん、日本がITを発展させていく必要性はありますが、それがメンタルヘルスに悪影響を及ぼすケースも少なくありません。
賢悟:やはり国やメディア、企業の働きかけが十分ではないと感じます。この問題に対して、実際には誰もがあまり働きかけていないように思えます。もちろん、日本がITを発展させていく必要性はありますが、それがメンタルヘルスに悪影響を及ぼすケースも少なくありません。
他人の生活を羨ましく思ったり、傷ついたりする子どもたちもいるのが現実です。スマホ使用においてはバランスが大切だと思うのですが、石井さんにとって理想的なスマホとの付き合い方はありますか?
石井:スマホから得られるスキルと、リアルな生活の中で得られるスキルは本質的に異なることをまず認識しなければなりません。スマホを持つこと自体は問題ではありませんが、その使用時間がリアルな世界で得られるスキルの向上に繋がらないということです。 今の子どもたちの環境では、スマホでは得られない経験、例えば人との関わりや実際の体験を通じて感じること、恐怖や不安を乗り越えることなどが不足しています。
そのため、学校や保育園、家庭が意識して、こうした体験を増やしていく必要があると思います。 基礎的な体力や生きる力を育てる中で、スマホの正しい使い方を学ぶことができれば、スマホを武器として活用することができるでしょう。中学生になると受験勉強などが始まり、スマホに依存しがちになるため、その前にしっかりとした土台を作ることが重要です。
土台がしっかりしていれば、子どもたちは自分がスマホを使いすぎていると認識できるようになります。また、ニュースで取り上げられるような、「東大に入るためにスマホをやめた」といった情報もありますが、スマホをやめただけで東大に入れるわけではありません。その意識は、前提となる基礎力があってこそ生まれるものだと思います。
スマホを使っていない時の充実感
 佐藤:スマホをしまうという行為が心地良さに繋がるという体験もあると思います。スマホを手放すことで勉強に集中できたり、すぐに寝られたりなど、心地よい感覚を味わうことで、スマホに依存しすぎない生活を促すことができるのかなと。
佐藤:スマホをしまうという行為が心地良さに繋がるという体験もあると思います。スマホを手放すことで勉強に集中できたり、すぐに寝られたりなど、心地よい感覚を味わうことで、スマホに依存しすぎない生活を促すことができるのかなと。
石井:そうですね。スマホを使わない時間をどれだけ充実させられるかが、子どもたちにとって大きな鍵になります。特に食事の時間は、家族とのコミュニケーションを育む大切な機会です。親子の会話が楽しいと感じられれば、自然とスマホを手放す理由が生まれますよね。
また、スマホを使わない時間に他のアクティビティや交流を取り入れることで、子どもたちがその時間を充実したものとして感じることができれば、スマホに依存する必要がなくなるかもしれません。こうした習慣を身につけることで、彼らの生活の質が向上することが期待できます。
大悟:たしかに、部活に一生懸命に取り組んでいる子たちは、自分でプロテインを摂取したり、睡眠時間をしっかり確保しなければならないという考えが浸透していますよね。私たちが望んでいるスマホとの付き合い方は、すでに部活に励む学生が体現しているのかなと思いました。
佐藤:なるほど。リアルな体験をしている子どもたちにとって、スマホはツールの一つとして認識されることもあるのですね。この話を聞くと、少し希望があるようにも感じました。
賢悟:貴重な話をしていただき、ありがとうございました! 石井:こちらこそありがとうございました!


